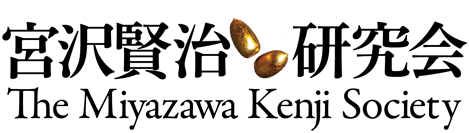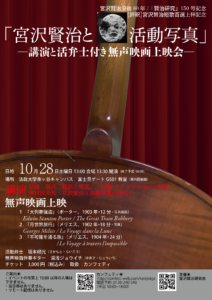| 例会時間割 | ||
| 開催日 | 令和5(2023)年12月2日(土) | |
| ※ 会場(渋谷区氷川区民会館)での対面方式による発表となります。また、リモート形式の配信も行います。リモート例会お問合せフォームより申込みいただいた方に招待状を送付します(下記の説明を参照願います)。 | ||
| 開始時間 | 所要時間目安 | 内 容 |
| 13:00 | 30分 | 開場、渋谷区氷川区民会館、Zoomアカウント開始、案内等 |
| 13:30 | 1時間程度 | 例会発表 深田愛乃氏(会場での対面方式。リモート配信あり) |
| 14:30 | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 14:45 | 15分程度 | 休憩・案内 |
| 15:00 | 1時間程度 | 例会発表 牧 千夏氏(会場での対面方式。リモート配信あり) |
| 16:00 | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 17:00 | 終了、退出。対面とリモートの混合方式の場合は「リモートの懇親会」はありません。 | |
| ※特に参加費は必要ありませんが会員限定です。会員でない場合はどうしたらよいか? |
※ 発表者お二人とも、会場での対面方式の発表になります。リモート配信もあります。会場はいつもの渋谷区氷川区民会館です。
そこで本発表では、賢治の実践やテクストを重点に置きながら、賢治と瑞彦、嘉藤治、武雄の具体的な活動を対照させる。瑞彦は童話や国語・図画教育、またよく知られるように嘉藤治は音楽教育、武雄は図画教育が、新教育を介した賢治との共有点のひとつをなしたと考えられる。最終的に、賢治を取り巻く新教育の思想圏では独特な芸術による人間形成への関心が共有されていたこと、しかし賢治の場合には「農」の思想を基底においた点で独自性を見せたことを仮説的に描き出したい。
(慶應義塾大学非常勤講師)
※会場における対面方式の発表です。
宮沢賢治の詩「産業組合青年会」は、福島県の同人詩誌『北方詩人』に掲載された。この『北方詩人』では、「産業組合青年会」掲載時から数編の宮沢賢治評が掲載された。『北方詩人』同人による評価をみると、彼らが宮沢賢治の、有名な詩人でなかった点、東北に在住していた点、アマチュア詩人であった点に注目していたことが分かる。こうした特徴は宮沢の要素でもあるが、それ以上に『北方詩人』同人が強調した彼ら自身の特徴であった。このことを踏まえ、『北方詩人』の消息欄から分かる同人の学歴、職業、詩との向き合い方などを明らかにしつつ、それがどのように宮沢賢治評価と重なるかを明らかにする。そうすることで、東北アマチュア詩人のあいだで、宮沢賢治がひとつの理想的な東北アマチュア詩人として捉えられていたことを指摘したい。
(長野工業高等専門学校 リベラルアーツ教育院 准教授)
※会場における対面方式の発表です。