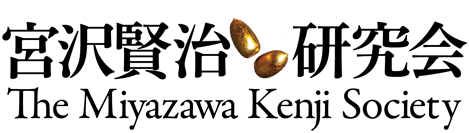7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)
4月第303回例会のご案内
| 開催日 |
開場 |
| 会場 |
開会 |
| 会場整理費 |
※ 今回から夜時間の開催です。
[box title=”発表者と演題” color=”#a9a9a9″](前半)![]() 栗原 文子(くりはらあやこ)氏
栗原 文子(くりはらあやこ)氏
パシフィック、三陸のどこかの海岸?!
作品『楢の木大学士の野宿』―野宿第三夜―
岩手県宮古市”浄土ヶ浜”は新生代古第三紀(6600万年前~2300万年前)の浜である。”蛸の浜”は浄土ヶ浜に隣接する浜であり、中生代白亜紀(1億4500万年前~6600万年前)のものだ。
賢治は大正6(1917)年7月、これらの浜辺を訪ねていると推定される。
昨年の平成30(2018)年5月5日、『楢の木大学士の野宿』が収録されている文庫本片手にその”蛸の浜”を訪ねてみた。
すると目の前に、「どうも斯う人の居ない海岸などへ来て、・・・どうだ、この頁岩の陰気なこと。」、「崖の脚には多分は濤で/削られたらしい小さな洞があったのだ。」、そして物語のクライマックスと思われる箇所で大学士が思わず発した「・・・事によったら新生代の沖積世が急いで助けに来るかも知れない。さあ、もうたったこの岬だけだぞ。」等々、作品中に書かれている風景がそっくりそのまま広がっていたのである。
もちろん、作品に書かれている一文一文は奇想天外にして抽象度高く、誰も追いつくことなどできない魅力にみちていることを再認識した。その感激を話すことができればと思う。
(会員)
(後半)![]() 板垣 寛(いたがきひろし)氏
板垣 寛(いたがきひろし)氏
賢治の心を生活に活かし、地域に活かし、未来に生かす
=その年間行事のあゆみ=
1 巨大氷柱たろし瀧の測定保存会の活動
毎年2月11日 於:奥羽山脈地内現地 たろし滝賛歌の合唱など
2 三月祭の開催
毎年3月10日 於:道の駅いしどりや 精神歌の合唱
3 やまなし祭の開催 毎年8月3日 於:やまなし植林地
やまなし賛歌の合唱
4 賢治葛丸祭の開催 於:葛丸ダム湖畔
毎年体育の日 葛丸賛歌の合唱
5 賢治作品音読会の開催 於:生涯学習会館
毎年奇数月の後半月曜日
6 父亮一の「おふくろの昔話」の紙芝居の開催
於:市内小学校、老人施設 毎年随時
(宮沢賢治学会イーハトーブセンター会員、石鳥谷賢治の会初代会長)
3月短歌読書会
7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)
2月第302回例会のご案内
| 開催日 |
開場 |
| 会場 |
開会 |
| 会場整理費 |
※ 午後時間の開催です。
[box title=”発表者と演題” color=”#a9a9a9″](前半)![]() 本田 裕子(ほんだゆうこ)氏
本田 裕子(ほんだゆうこ)氏
『銀河鉄道の夜』と「天の川」との距離
以前に『銀河鉄道の夜』での「天の川の水」について発表した(平成二十九年六月『銀河鉄道の夜』における「天の川の水」)が、今回はそれとはまた別のベクトルとして、ジョバンニと「天の川」を考えたい。
本作の全ての次稿で描かれている、ジョバンニの悲しみ。その中で「天の川」がどのように描かれているのかを探り、関係性を述べたい。
ジョバンニが難破船の少女とカムパネルラの仲良さに、「つらい」、「かなしい」と思い始め、不機嫌になる。その時に「天の川」はジョバンニから離れて、「たうもろこし畑」の風景になる。その後も「天の川」の風景ではない時、ジョバンニは不機嫌である。しかし、「天の川」に車窓から見え始めたことにより、ジョバンニの機嫌がよくなり、不機嫌になることはなくなり、「天の川」は汽車の傍らで流れ、離れることはなくなった。
以上のことを踏まえると、ジョバンニと「天の川」が連動していると想像できる。
(会員)
(後半)![]() 正海 澄恵(しょうかいすみえ)氏
正海 澄恵(しょうかいすみえ)氏
「私の宮沢賢治」
高校生の時に宮沢賢治に魅せられて以来、作品に触れ伝記や研究書を読み、自分なりの賢治像を追いかけてきた。生誕100年、120年などの賢治ブームもあり、TVや雑誌の特集などでも幾度となく取り上げられ、関連書籍も毎年多く出版され続けていて、一般的な賢治像はそれらによる部分も大きいと思う。資料の発見や調査によって近年あきらかになったことも多々ある中で、私の賢治像も当初とはかなり違ってきている。広く知れ渡った一般的な賢治像の変遷とはある程度は同期しているはずである。その辺りの経緯を振り返り、比較をしながら、地方の一賢治ファンの「私の宮沢賢治」を話してみたい。
(会員)
1月短歌読書会
7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)