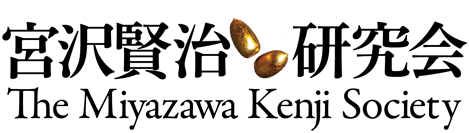7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)
2月第308回例会のご案内
| 開催日 |
開場 |
| 会場 |
開会 |
| 会場整理費 |
※ 午後時間の開催です。
[box title=”発表者と演題” color=”#a9a9a9″](前半)![]() 鈴木 太二(すずきたいじ)氏
鈴木 太二(すずきたいじ)氏
ガドルフと修験道
―もう一度生まれ変わるため― +朗読「ガドルフの百合」
放浪の旅を続けるガドルフ。その旅の最中降りかかる雷雨の中で、ガドルフは「稜が五角で、巨きな真っ黒な家」を見つけ、雨を凌ぐ為その中へと入っていく。
この唐突に現れた建物は、法華経で言うところの「化城宝処の喩え」を彷彿とさせる。道を求めて進むものが困難や苦難を前にしたとき、「化城」を出現させて休息を与え、再び歩み出させる仏の慈悲をいう喩えであり、「ガドルフの百合」を、ひいては宮沢賢治を愛する諸兄に於かれてはご存知の方も多いと思う。
しかし私は今回この作品を語り、演じるにあたって、この建物が今後の展開にどう生きるかもう少し考えてみた。すると思い当たったのが、修験道における修行宿の存在、そして子宮を意味する五芒星(五角形)の魔法陣の存在だった。
修行宿という別世界に入り、暗い胎内をくぐり、物を探り、触れ、幻燈のような幻を観る。
心象と現実が同期したような現象を経て、ガドルフはそれまでとは違う自分へと生まれかわろうとしていたのか。修行の各工程と描写を照らし合わせながら、実際に作品を朗読しつつ確認してみたい。
(ものがたりグループ☆ポランの会)
(後半)![]() 深田 愛乃(ふかだあいの)氏
深田 愛乃(ふかだあいの)氏
宮沢賢治の教育思想
―農学校での実践と文学作品を手がかりに―
これまでにも、賢治の教育者としての顔と仏教者としての顔は様々な角度から検討されてきた。特に、教育者としては農学校での教科書を使わない独特な授業実践が、仏教者としては『法華経』や国柱会との関連が着目されてきた。しかし、こうした賢治の両面は各々分離して検討されてきたように見える。それは、教壇上での賢治は自身の法華経信仰を語ったり折伏的態度を見せたりすることがほとんどなかったために、一見両者が結びつかないように見えることによるものと思われる。
そこで発表者は、賢治の教育思想の背後にある『法華経』を中心とした信仰世界による影響を探ることに関心を持ち研究を進めている。修士論文では、
(1)農学校教師としての教育実践
(2)国民高等学校から羅須地人協会時代
(3)賢治の文学作品に見る教育思想
(4)教師・宮沢賢治と信仰世界
の4本立てで検討を行った。本発表では、そのうちの(1)(3)における農学校での教育実践や童話作品を中心に取り上げる。よって、今回は真宗から『法華経』・国柱会へという信仰遍歴に関してはあまり言及しないこととなるが、賢治の教育に通底する法華経信仰の影響を垣間見る序説としたい。
(慶應義塾大学大学院修士課程・会員)
1月短歌読書会
7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)
12月第307回例会のご案内
| 開催日 |
開場 |
| 会場 |
開会 |
| 会場整理費 |
※ 午後時間の開催です。
[box title=”発表者と演題” color=”#a9a9a9″](前半)![]() 伊藤 雅子(いとうまさこ)氏
伊藤 雅子(いとうまさこ)氏
裏読み「土神ときつね」
―女難の始まり―
本作は女の樺の木に恋した土神が、恋敵の狐に嫉妬し無礼に逆上して殺す話。非常に生々しくて、つい賢治が巻き込まれたのではと疑ってしまう。
土神と狐を賢治の分身とみる説がある。筆者はそれにとどまらず樺の木にも賢治の影が濃いと感じる。たとえば花巻高女同窓生の間で良縁と認識されたはず。嫉妬の火花が散ったとしてもおかしくない。
土神をドジンと発音したときの駄洒落、創作メモ、執筆年代を考え合わせると、某女の存在に気づく、樺の木と土神と狐は、某女の性格を三分割し、賢治の性格を混ぜて三者の個性とし、関係者をぼかしたうえで、横恋慕による破局を描いたのでは?以上の仮説のもと本作内外を検討したい。
(会員)
(後半)![]() 萩原 昌好(はぎわらまさよし)氏
萩原 昌好(はぎわらまさよし)氏
羅須地人協会の頃の賢治
発表趣旨
(1)なぜ羅須地人協会へ移ったのか。
宗教的動機
父からの脱出
(2)「農民芸術概論」と地人への道
(3)新たな在家仏教信仰者として
国柱会から新信行へ
(4)河口慧海の「在家仏教」論
(5)高瀬 露と伊藤チヱ
以上の五点から、彼の言う「修羅の成仏」への過程を再検討する。
(埼玉大学名誉教授・会員)
11月短歌読書会
7月読書会の記事を投稿しました。今回は、会場がいつもの千駄ヶ谷区民会館と異なりますので、ご注意ください。(6月16日)