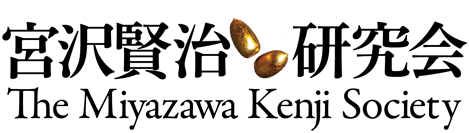| 開催日 |
開場 |
| 会場 |
開会 |
| 会場整理費 |
※ 夜時間の開催です。
[box title=”発表者と演題” color=”#a9a9a9″](前半)![]() 正木 晃(まさきあきら)氏
正木 晃(まさきあきら)氏
宮澤賢治の法華経信仰
先年、国際日本文化研究センターで宮澤賢治を対象とする研究会が開催された折、痛感したことがあった。賢治研究者の伝統仏教に関する知見が、きわめて乏しかったのである。とりわけ賢治が帰依していた法華経については絶望的なほど無知であった。それどころか、代表的な研究者の中にも、あえて無視しようとするかのような態度が見られた。今回の発表では、これらの事実をふまえて、賢治の法華経信仰について述べたい。
(宗教学者)
(後半)![]() 杉浦 静(すぎうらしずか)氏
杉浦 静(すぎうらしずか)氏
大正一〇年の〈東京〉体験
―「「東京」ノート」の短歌・スケッチ・散文から考える
「「東京」ノート」中の「〔東京〕」の章は、「歌稿〔B〕」や失われた〈東京のスケッチ〉とも呼ぶべきスケッチ集から抜き出された(と推定される)短歌連作及び短唱(スケッチ)からなっている。このうちの「一九二一年一月より八月に至るうち」の中には、題材の日時がほぼ特定できるものがいくつかある。それらから、この章は書かれた日付順に並んでいると推測される。この章に並ぶスケッチのうち、タイトルの付されているのは「公衆食堂(須田町)」と「孔雀」の二篇のみである。章末に断片的に記された「◎図書館(ダールケ博士)」「◎床屋の弟子とイデア界」「◎」は、この章に入れるはずであった散文作品のタイトルと推測され、それぞれ〈初期短篇綴等〉の「ダルゲ」「床屋」「電車」が対応していると思われる。今回の発表では、これらの複数のジャンルのテクストに表象された、賢治のこの時の〈東京〉体験の意義をあらためて考えてみたい。
(会員、大妻女子大学教授)