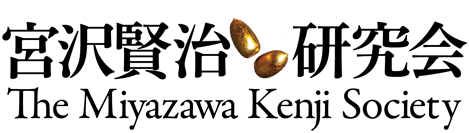| 例会時間割 | ||
| 開催日 | 令和7(2025)年8月2日(土) | |
| ※ 会場(氷川区民会館)を確保しています。また、リモート形式の配信も行います。リモート例会お問合せフォームより申込みいただいた方に招待状を送付します(下記の説明を参照願います)。 | ||
| 開始時間 | 所要時間目安 | 内 容 |
| 13:00~ | 30分 | 開場 氷川区民会館 、Zoomアカウント開始、案内等 |
| 13:30~ | 1時間程度 | 研究発表 村上英一氏(会場対面予定) |
| 14:30~ | 20分程度 | 質疑応答(〃) |
| 14:50~ | 15分程度 | 休憩・案内 |
| 15:05~ | 1時間程度 | 研究発表 神田彩絵氏(会場対面予定) |
| 16:05~ | 20分程度 | 質疑応答(〃) |
| 16:30 | 終了、退出(17:00までに) | |
| ※特に参加費は必要ありませんが会員限定です。会員でない場合はどうしたらよいか? |
※ 前後半共々会場対面の予定です。リモート配信はあります。会場は氷川区民会館です。
※ 会場でご参加の方は、参加者名簿にご記入の上、整理費500円也をお納めください。
前半 演題と発表者 演題 「気のいい火山弾」を読む 村上英一(むらかみ・えいいち)氏
「気のいい火山弾」は、「よだかの星」や「猫の事務所」に通じるいじめを扱った作品、或いは「虔十公園林」に通じるデクノボー礼賛の作品とする読み方をされることも多いが、一方で、ベゴ石が実は相当に賢いことも指摘されている。実際、やり取りを見ると、悪口に対して巧みに受け流しており、語り手も、「稜のある石ども」が「たゞからかったつもりだっただけ」だと述べている。
ベゴ石が火山弾の標本としての価値を認められ、「東京帝国大学校地質学教室」へ送られるラストは、価値観の逆転やベゴ石の立身出世と捉えられることも多いが、ベゴ石自身は、「私の行くところは、こゝのやうに明るい楽しいところではありません。」と述べ、必ずしも喜んでいないどころか、むしろ寂しげでさえあることが問題とされている。ベゴ石は、馬鹿にされながらも野原にいて幸せだったと思われるが、そこをあまり重くみると、野原から連れ出される作品の結末は、悲劇となってしまう。「私共は、みんな、自分でできることをしなければなりません。」というベゴ石の言葉をどのように解したらよいのか、この作品を改めて検討してみたい。
(本会会長)
※会場における対面による発表+リモート配信。
ベゴ石が火山弾の標本としての価値を認められ、「東京帝国大学校地質学教室」へ送られるラストは、価値観の逆転やベゴ石の立身出世と捉えられることも多いが、ベゴ石自身は、「私の行くところは、こゝのやうに明るい楽しいところではありません。」と述べ、必ずしも喜んでいないどころか、むしろ寂しげでさえあることが問題とされている。ベゴ石は、馬鹿にされながらも野原にいて幸せだったと思われるが、そこをあまり重くみると、野原から連れ出される作品の結末は、悲劇となってしまう。「私共は、みんな、自分でできることをしなければなりません。」というベゴ石の言葉をどのように解したらよいのか、この作品を改めて検討してみたい。
(本会会長)
※会場における対面による発表+リモート配信。
後半 演題と発表者 演題 イーハトーブにおけるキツネの諸相 ―『宮沢賢治の動物誌』より― 神田彩絵(かんだ・さえ)氏
本発表では、2025年2月に刊行した『宮沢賢治の動物誌 ―キャラクターを織り上げる―』より、イーハトーブ童話におけるキツネの諸相を取り上げて考察する。
本書では、宮沢賢治が創作した一連の童話群を、イーハトーブという共通の“異世界”の中で展開される地続きのテクストとして捉え、繰り返し登場する8種の動物を「キーアニマル」と位置づけて分析を行った。分析にあたっては、生物学や民俗学、日本および世界の古典文学から近現代文学までを幅広く参照し、イーハトーブにおける動物表象と比較することで、宮沢賢治の動物観の独自性を明らかにしている。
本発表では、その中からキツネに焦点を当てる。キツネは古来より日本人に親しまれ、神聖視されてきた動物であり、昔話から現代のコンテンツに至るまで、頻繁にキャラクターとして登場している。本発表では、イーハトーブにおけるキツネの表象を、日本における古代から現代までのキツネ観を中心に、生物学的知見や世界各地のキツネ観と比較することで、宮沢賢治のキツネ観の独自性とその文学的意義を浮き彫りにすることを目的とする。
(東京女子大学大学院人間科学研究科博士前期課程修了。専攻は日本近現代文学。論文に「宮沢賢治童話における〈クマ〉――他者として描くこと」(「東京女子大学日本文学」第118号)など。渋谷区立宮下公園で開催されたWedding Park 2100「Parkになろう」(2023年)でエッセー「豊かさは繋がること」を寄稿。
著書に、『宮沢賢治の動物誌 -キャラクターを織り上げる-』(青弓社・2025年2月)。)
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
本書では、宮沢賢治が創作した一連の童話群を、イーハトーブという共通の“異世界”の中で展開される地続きのテクストとして捉え、繰り返し登場する8種の動物を「キーアニマル」と位置づけて分析を行った。分析にあたっては、生物学や民俗学、日本および世界の古典文学から近現代文学までを幅広く参照し、イーハトーブにおける動物表象と比較することで、宮沢賢治の動物観の独自性を明らかにしている。
本発表では、その中からキツネに焦点を当てる。キツネは古来より日本人に親しまれ、神聖視されてきた動物であり、昔話から現代のコンテンツに至るまで、頻繁にキャラクターとして登場している。本発表では、イーハトーブにおけるキツネの表象を、日本における古代から現代までのキツネ観を中心に、生物学的知見や世界各地のキツネ観と比較することで、宮沢賢治のキツネ観の独自性とその文学的意義を浮き彫りにすることを目的とする。
(東京女子大学大学院人間科学研究科博士前期課程修了。専攻は日本近現代文学。論文に「宮沢賢治童話における〈クマ〉――他者として描くこと」(「東京女子大学日本文学」第118号)など。渋谷区立宮下公園で開催されたWedding Park 2100「Parkになろう」(2023年)でエッセー「豊かさは繋がること」を寄稿。
著書に、『宮沢賢治の動物誌 -キャラクターを織り上げる-』(青弓社・2025年2月)。)
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
■リモート例会のお申し込みについて/コロナ下における例会開催についての説明