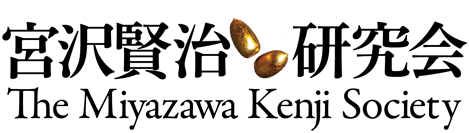| 例会時間割 | ||
| 開催日 | 令和7(2025)年6月7日(土) | |
| ※ 会場(氷川区民会館)を確保しています。また、リモート形式の配信も行います。リモート例会お問合せフォームより申込みいただいた方に招待状を送付します(下記の説明を参照願います)。 | ||
| 開始時間 | 所要時間目安 | 内 容 |
| 13:00~ | 30分 | 開場 氷川区民会館 、Zoomアカウント開始、案内等 |
| 13:30~ | 1時間程度 | 研究発表 栗原文子氏(会場対面予定) |
| 14:30~ | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 14:50~ | 30分程度 | 総 会 |
| 15:20~ | 10分程度 | 休憩・案内 |
| 15:30~ | 1時間程度 | 研究発表 水野達朗氏(会場対面予定) |
| 16:30~ | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 16:45 | 終了、退出(17:00までに) | |
| ※特に参加費は必要ありませんが会員限定です。会員でない場合はどうしたらよいか? |
※ 前後半共々会場対面の予定です。リモート配信はあります。会場は氷川区民会館です。
※ 会場でご参加の方は、参加者名簿にご記入の上、整理費500円也をお納めください。
前半 演題と発表者 演題 『賢治の短歌や詩から浮かぶ新たなる風景』 栗原文子(くりはら・あやこ)氏
とびきり意外で、響きの美しい語句が散りばめられている賢治の短歌や詩には、何回読んでも、新たな発見がある。詠まれてからあと少しで百年が経つというのに、その語句を見て知ったが最後、よく意味がわからなくても、金輪際忘れることができなくなったりするのであるから、全く天才賢治は人騒がせである。
先ごろ、地質学者の高橋雅紀氏より、賢治作品に登場するあちこちの地質や岩礁について、興味深い知見を教えていただく機会を得て、筆者は目下、“先生の眼はヨハネのごとし”、“ボルドウ液の霧ふりて”、“粋なもやうの博多帯”、“ミンナニデクノボート ヨバレ”などに夢中である。
早速、その知見をヒントに耳目をフルに働かせ、これらの語句から立ち上がってくる賢治でこその風景を想い描いてみたい。
(本会会員)
※会場における対面による発表+リモート配信。
先ごろ、地質学者の高橋雅紀氏より、賢治作品に登場するあちこちの地質や岩礁について、興味深い知見を教えていただく機会を得て、筆者は目下、“先生の眼はヨハネのごとし”、“ボルドウ液の霧ふりて”、“粋なもやうの博多帯”、“ミンナニデクノボート ヨバレ”などに夢中である。
早速、その知見をヒントに耳目をフルに働かせ、これらの語句から立ち上がってくる賢治でこその風景を想い描いてみたい。
(本会会員)
※会場における対面による発表+リモート配信。
後半 演題と発表者 演題 「春と修羅・第二集」下二推敲における表現手法の諸相 水野達朗(みずの・たつろう)氏
「春と修羅・第二集」は「賢治の亡くなる昭和八年まで」の推敲の累積だが、作中期間である「大正十三年、十四年」の枠にとらわれ、教師から農民への「過渡的なものと見なされる傾向」があると入沢康夫は述べた(全集解説)。「第二集」が過渡期の記録として読まれるのを可能にした詩句(例えば杉浦静が指摘した「農事」をめぐる記載)には推敲終盤(昭和五年以降か)で追加されたものが多い。
すぐ削除されたものも含めてこの段階で出現する詩句では、農学校教師としての農村との関係や、農村を苦しめた旱害に対する意識を踏まえて新たな道に踏み出すという主題が浮上する。またこうした「現実的」な内容の流入に対して、推敲初期からの「異空間」の構想や、比喩的な世界認識の手法を改めて構築し直すという方向性も現れてくる。
本発表では、初期の表現様式を検討した拙稿「「春と修羅・第二集」下一初形における表現手法とその変容―「二重の風景」の詩学―」(『宮沢賢治研究annual』三四号)を承け、「第二集」の世界を貫く「二重の風景」がこうして初期段階とは別の形で再構成されていく様相を跡付ける。
(本会会員・大学非常勤講師)
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
すぐ削除されたものも含めてこの段階で出現する詩句では、農学校教師としての農村との関係や、農村を苦しめた旱害に対する意識を踏まえて新たな道に踏み出すという主題が浮上する。またこうした「現実的」な内容の流入に対して、推敲初期からの「異空間」の構想や、比喩的な世界認識の手法を改めて構築し直すという方向性も現れてくる。
本発表では、初期の表現様式を検討した拙稿「「春と修羅・第二集」下一初形における表現手法とその変容―「二重の風景」の詩学―」(『宮沢賢治研究annual』三四号)を承け、「第二集」の世界を貫く「二重の風景」がこうして初期段階とは別の形で再構成されていく様相を跡付ける。
(本会会員・大学非常勤講師)
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
■リモート例会のお申し込みについて/コロナ下における例会開催についての説明